制作会社が考える、Web発注にあたっての準備・体制の話
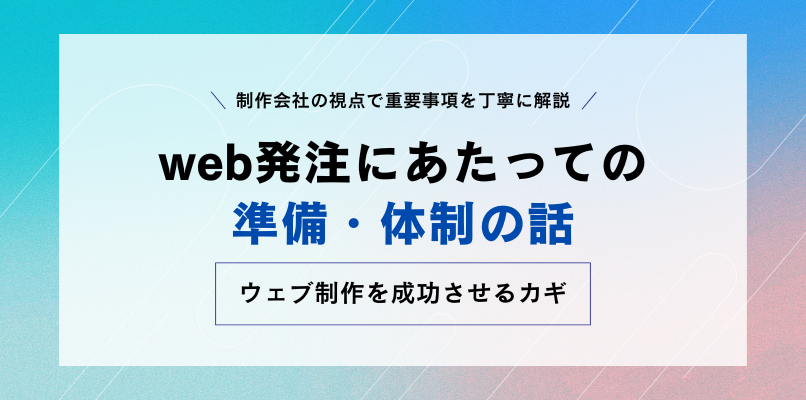
制作会社にホームページ制作を依頼するにあたって、何をどう準備すれば良いかわからないという方は多いんじゃないでしょうか。
こうするとスムーズにいきますよ、とかこういうったものを用意してください、というものは打ち合わせの際にお伝えいたしますが、事前にある程度把握しておきたいというお客様もおられると思いますので、大まかな進め方や注意点、制作会社からの願望などもふまえてなるべくわかりやすく記事にしようと思います。
まず絶対必要なもの筆頭、どういうサイトを作るのかという構想
いきなり馬鹿にするんじゃないよ、とお思いの方も居るかもしれませんが、これは一番大事なんです。
はじめての発注の場合に多いのですが、会社のコーポレートサイトを作るのか、商品のサイトを作るのか、商品は紹介なのか販売なのか、意外と定まっていない方がおられます。
世の中にはどういったサイトがあるのかというのを見ていきましょう。
企業情報サイト
コーポレートサイトとも呼ばれ、会社の紹介のサイトです。
まずはじめにこれを作るという場合が多いです。
今では何か事業を行うにあたって、企業情報サイトは必須とも言えるサイトです。
現状仕事が十分回っているので必要ない、と思われる方も居るかもしれませんが、ホームページ、特に企業情報サイトというのは必要になった際に急に作るというものでは無く、長年にわたって育てていくものです。
SEO面でも、長期にわたって運営しているドメインはGoogleから評価されやすく、被リンクも長期的に獲得していくものです。
サイトが無いというのは事業として非常に勿体ないので、まだ作られていない企業様は是非作成することをお勧めします。
近年ではWordpressなどのCMSを利用するケースが増えていて、digrartでもWordpressの案件は非常に多いです。
ブランドサイト
次に挙がるのがブランドサイトですね。これは特定の製品やサービス、あるいは企業全体のブランドイメージを伝えることに特化したサイトです。企業情報サイトが会社の「顔」だとすれば、ブランドサイトは製品やサービスの「魅力」を最大限に引き出すための場所と言えます。
例えば、新商品の発売に合わせてその商品の世界観を表現したり、特定のキャンペーンに合わせて特設サイトを設けたりします。デザインの自由度が高く、写真や動画を多用して情緒的な体験を提供することで、ユーザーの心を掴むことを目的とすることが多いです。企業情報サイトがある上で、さらに特定のターゲット層に深くアプローチしたい場合に検討すると良いでしょう。
ECサイト(ネットショップ)
そして、商品をインターネット上で販売したい場合に必要になるのがECサイト、いわゆるネットショップです。これはもう、単なる情報提供サイトではなく、決済機能や在庫管理、顧客管理といったシステムが不可欠になります。
一言でECサイトと言っても、扱う商品の種類や数、販売形態によって求められる機能は大きく異なります。Amazonや楽天のようなモールに出店するのか、自社で独自のECサイトを構築するのかによっても、かかる費用や手間は大きく変わってきます。まずは「何を、誰に、どう売るのか」を明確にすることが、ECサイト構築の第一歩になります。
ECサイトは他のサイトに比べて商品の入れ替え、管理、発送、顧客対応等に多くの時間と人員が必要です。
そういった体制の事も考えておく必要があります。
LP(ランディングページ)
最後に紹介するのはLP(ランディングページ)です。これは、特定の広告からの流入など、ユーザーが最初に着地する(ランディングする)ことを目的とした、一枚完結型のウェブページのことです。
LPの主な目的は、商品購入や資料請求、問い合わせなど、特定の行動をユーザーに促すことにあります。そのため、通常のウェブサイトとは異なり、メニューや他のページへのリンクが最小限に抑えられ、ユーザーの注意を逸らさないような構成になっています。デザインも非常に重要で、短い時間でユーザーの心を掴み、行動へと誘導するための工夫が凝らされます。特定のキャンペーンや新商品の宣伝など、短期的な成果を求める場合に非常に有効な手段です。
短期的なキャンペーンページなども多く、そういった場合にはSEOよりもリスティング広告での集客が重要視されます。
採用サイト
その他、最近特にニーズが高いのが採用サイトです。企業情報サイトでも採用情報は掲載できますが、採用に特化した専門のサイトを作ることで、会社の魅力や働きがい、社員の声などをより深く、多角的に伝えることができます。人材確保が難しくなっている現代において、優秀な人材を獲得するために採用サイトは非常に重要な役割を果たします。
会社の文化や働く環境、キャリアパスなどを具体的に見せることで、求職者にとって魅力的な情報源となり、ミスマッチを防ぐ効果も期待できます。動画や社員インタビューなどを活用して、リアルな会社の雰囲気を伝えることも可能です。
一度作ってしまえば、転職サイトや転職エージェントにかけるコストを削減できることも魅力です。
ウェブ制作を成功させるカギ!社内の体制と担当者の選び方
さて、どういうサイトを作りたいかが漠然とでも見えてきたら、次に大事になってくるのが、社内の体制、特にプロジェクトの担当者についてです。
正直なところ、私たち制作会社にとって、この部分がスムーズに進むかどうかでプロジェクトの成否が大きく分かれると言っても過言ではありません。打ち合わせで細かく詰めて、デザインもシステムもOKをいただいたのに、制作後に社長が全部ひっくり返すなんてことになったらもう目も当てられません。
このようなケースは実際にあります。通常はそういった場合に無償でやり直しをする制作会社はありませんので、クライアントにとっても無駄なコストとなってしまいます。
また、ご担当者様が多忙でなかなかレスポンスがいただけなかったり、社内で意見がまとまらず何度も同じやり取りを繰り返したり…。こういう状況が続くと、プロジェクトの期間が当初の予定より大幅に延びてしまい、結果的にお客様にとっても、私たちにとっても望ましくない結果になってしまいます。
そうならないためにも、ぜひ以下の点を考慮していただきたいんです。
① 意思決定者を明確にする
プロジェクトの初期段階で、最終的な意思決定権を持つ方が誰なのかを明確にしてください。できれば、その方にプロジェクトの途中段階でも適宜レビューに参加していただき、方向性のズレがないかを確認してもらえると理想的です。
「担当者と打ち合わせは重ねたけど、最後の最後で上層部からNGが出た」という事態は、時間も費用も無駄にしてしまう最大の要因です。最終決定権を持つ方が早い段階から関わることで、手戻りが格段に減りますよ。
② 専任の担当者を立てる
兼任で別の業務も抱えているのは当然だと思いますが、できる限りウェブ制作プロジェクトの専任担当者を立てていただけると非常に助かります。少なくとも、私たちからの連絡に対して迅速に対応できる体制を整えていただきたいです。
制作はキャッチボールのようなもので、私たちの提案に対してお客様からのフィードバックが滞ると、その分だけボールが止まってしまい、プロジェクト全体が停滞してしまいます。日中の業務時間外でも、メールチェックだけでも可能かなど、コミュニケーション方法とタイミングも最初に決めておくと良いでしょう。
③ 社内での意見集約と連携
社内で複数部署が関わる場合は、事前に意見をまとめ、窓口を一本化していただくことをお勧めします。部署ごとに意見が異なると、制作側としては何を正として進めれば良いか分からなくなってしまいます。
打ち合わせの前に社内で十分な検討を重ね、担当者が責任を持って決定を下せるように準備をしていただくことが、スムーズな進行には不可欠です。社内での情報共有や連携が密に行われていると、プロジェクトは驚くほど早く進みますよ。
ウェブサイトの顔!写真と動画のクオリティは妥協しないでほしい
次に考えておいてほしいのは、写真(必要な場合は動画)をどうするかという事です。
現代のウェブサイトにおいて、高いクオリティの写真や動画は、もはや「あればいい」レベルの話ではなく、「必須」と言っていいほど重要になっています。
せっかく多額の費用と時間をかけて素晴らしいデザインのウェブサイトを作っても、そこに掲載されている写真がスマートフォンのスナップ写真だったり、照明が不十分な室内で撮られたような写真だったりすると、残念ながらサイト全体の印象が台無しになってしまいます。まるで高級レストランで出てきた料理が、自宅で適当に作ったような盛り付けだったらガッカリするのと同じです。
ウェブサイトは、お客様や見込み客があなたの会社や商品に触れる「最初の接点」となることがほとんどです。そこで視覚的に訴えかける力が弱いと、せっかくの魅力も半減してしまいます。良い写真や動画は、言葉では伝えきれない情報や感情を瞬時に伝える力があります。
プロのカメラマンに依頼するメリット
もちろん弊社でも写真撮影や動画制作のご依頼を承ることは可能です。ただ、それが必須というわけではありません。しかし、お客様側で写真や動画を用意される場合でも、プロのカメラマンに依頼することを強くお勧めします。
プロのカメラマンは、単に「綺麗に撮る」だけではありません。ウェブサイトでの見せ方を理解し、光の当て方、構図、被写体の魅力を最大限に引き出す方法を知っています。製品写真であれば商品の質感を伝えるライティング、人物写真であればその人の個性や信頼感を表現する表情の引き出し方など、素人では到底及ばない技術と経験を持っています。
結果として、ウェブサイトの見た目だけでなく、貴社や貴社の商品・サービスの「価値」を格段に向上させることにつながります。ウェブサイト制作費用の何パーセントかを写真や動画の予算に割くことは、決して無駄な投資ではありません。むしろ、費用対効果の高い重要な投資だと考えていただきたいです。
適当に撮られた写真で終わらせるには、せっかく費用をかけて作るウェブサイトがもったいなさすぎますよ。
サイトの「中身」を形にする、原稿(テキストコンテンツ)の準備
ウェブサイトの見た目や機能ばかりに目が行きがちですが、実はその「中身」である原稿(テキストコンテンツ)の準備も非常に重要です。デザインがどんなに素晴らしくても、掲載する文章がなければサイトは完成しませんし、伝えたい情報が曖昧だと、せっかくのサイトもその役割を果たせなくなってしまいます。
制作会社はデザインやシステムを構築しますが、サイトに掲載する貴社の事業内容、商品・サービスの説明、会社概要、ブログ記事などの「文章」はお客様自身にご用意いただくのが基本です。この原稿の準備が遅れてしまうと、以下のような問題が発生し、プロジェクト全体の遅延や余計なコストにつながる可能性があります。
原稿がないとデザインも進まない?
「デザインができたから原稿を流し込む」と思われがちですが、実はそうではありません。制作会社は、お客様から提供された原稿のボリュームや内容に合わせて、最適なデザインを検討し、レイアウトを構成していきます。
例えば、「このセクションにはどんな情報をどれくらいの量で載せたいか」「伝えたいメッセージのポイントは何か」といったことが事前に分かっていると、より効果的なデザインを提案できます。
実際問題として、原稿が用意できずデザイン先行で制作するケースも少なくはないのですが、そういった場合にはどうしても攻めたデザインは出来ず画一的にならざるを得ませんし、後から文章を当てはめる際に「収まりきらない」「スカスカになってしまう」といった問題が生じ、手戻りが発生する原因となります。
プロジェクト遅延の最大の要因に
これまでの経験上、ウェブサイト制作のプロジェクトが遅れる一番の原因は「原稿の準備が間に合わない」ことです。制作会社側は、デザインやシステムの作業を待っていても、原稿が揃わないと次の工程に進むことができません。結果として、予定していた公開日が大幅にずれ込んだり、制作会社との間で納期に関する認識のズレが生じたりすることがあります。
原稿作成は、専門的な知識や表現力も求められる作業です。もし社内に担当者がいない、あるいはリソースが不足している場合は、制作会社にライティング代行を依頼することも検討してみてください。費用はかかりますが、プロが読者の心に響く文章を作成することで、サイトの質も格段に向上し、結果的に時間と労力の節約にもつながります。
SEOにも影響するコンテンツの質
単に文章を載せれば良いというわけではありません。ウェブサイトは検索エンジンからも評価されるため、ユーザーにとって有益な情報が分かりやすく書かれている必要があります。キーワードを意識した文章作成や、ターゲットユーザーが何を求めているのかを考えたコンテンツ設計は、公開後の集客にも大きく影響します。
制作会社と相談しながら、どのようなコンテンツが必要で、どのように表現すれば効果的なのか、早い段階から計画を立てておくことをお勧めします。魅力的なウェブサイトは、優れたデザインだけでなく、質の高いコンテンツがあってこそ成り立つのです。
ウェブサイト公開後の運用体制も忘れずに
サイトが完成し、いざ公開!となったら「やったー、これで終わり!」と思いがちですが、実はここからが本当のスタートなんです。ウェブサイトは作って終わりではありません。公開後の運用が、そのサイトが成果を出し続けられるかどうかの鍵を握ります。
例えば、新しい情報を更新したり、ブログを投稿したり、はたまたシステムに不具合が出た時の対応など、公開後も様々な作業が発生します。これらの運用を誰が、どのように行っていくのかを事前に考えておくことがとても大切です。
更新頻度と担当者を決める
ブログ記事の投稿や、お知らせの更新など、定期的に情報発信を行っていく場合、誰がどのくらいの頻度で更新するのかを具体的に決めておきましょう。もし社内に担当者がいない、あるいは手が回らないという場合は、私たち制作会社が保守・運用サポートとしてお手伝いすることも可能です。
更新が滞ると、せっかく作ったウェブサイトも「情報の古いサイト」と認識されてしまい、ユーザーからの信頼を失いかねません。SEOの観点からも、定期的な更新は非常に重要です。誰が、いつ、何を更新するのかを明確にしておくことで、公開後もサイトを「生き物」として育てていけるようになりますよ。
緊急時の連絡体制とセキュリティ対策
もしサイトに不具合が発生したり、サーバーに問題が起きたりした場合、誰に連絡すれば良いのか、どういった対応が必要になるのかを事前に確認しておくことも非常に大切です。特にWordPressなどのCMSを利用している場合は、定期的なプラグインやテーマの更新、PHPバージョンのアップデートなど、セキュリティを維持するための運用も欠かせません。
「うちは大丈夫だろう」と油断していると、ある日突然サイトが表示されなくなったり、悪意のある攻撃の標的になったりする可能性もゼロではありません。緊急時の連絡先や、日々のセキュリティ対策についてもしっかりと計画し、必要であれば制作会社に保守・管理を依頼することも検討してみてください。せっかく作った大切なウェブサイトを守るためにも、ぜひ考えておきたい点です。
頭でっかちにならず、まずはご相談を
今回この記事で取り上げたような、体制であったり準備のようなものは大切ですが、考えすぎてはじめの一歩を踏み出せないのでは意味がありません。
こういった事は打ち合わせでもお話しますし、我々と一緒に内容を詰めながら考えても大丈夫な部分もあります。
「こういう事が必要なんだな」とだけ捉えていただければOKですので、考えすぎず、まずはお問い合わせ頂ければと思います。

この記事を書いた人
大阪市中央区にて2009年よりWeb制作・運用支援を行い、1,000件以上の実績を持つWeb制作会社「digrart(ディグラート)」編集部が、本記事を執筆・監修しています。
現場で培った豊富な知見を活かし、Webサイト制作、ECサイト制作、SEO対策、Webコンサルティングの実践的なハウツーをお届けします。
初心者からプロまで、Web戦略の成功をサポートする実務ベースの情報が満載です。
関連記事
-

Webサイトは「作る前」が肝心!最新SEOで差をつける集客コンテンツ戦略
「せっかくWebサイトを作ったのに、全然問い合わせが来ない…」 「作ったはいいけれど、アクセスが伸びなくて困っている」 こんなお悩み、ありませんか? 多くの...
-
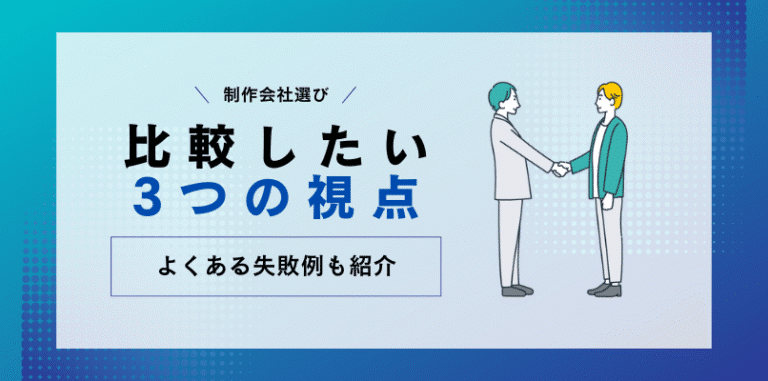
ホームページ制作会社選びで比較したい3つの視点とよくある失敗例
ホームページ制作を外注する際、最も重要なのが「どの制作会社を選ぶか」です。 しかし、料金や実績だけで選んでしまい、完成後に「思っていたものと違う…」と後悔する...
-
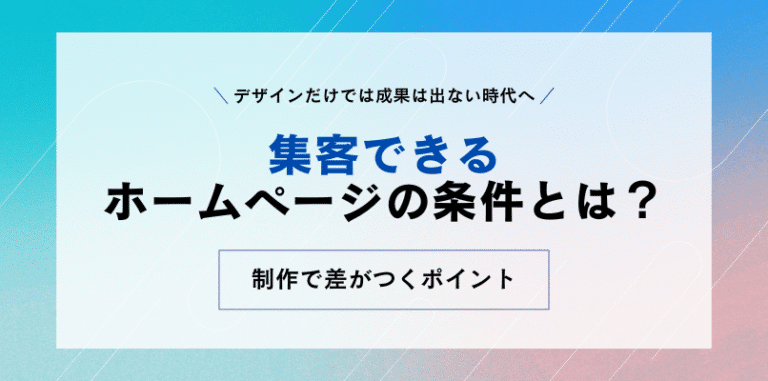
集客できるホームページの条件とは?制作で差がつくポイント
ホームページを作る目的が「名刺代わり」から「集客・売上向上」へと変化している今、ただ見た目が整っているだけでは効果は出ません。重要なのは、「集客につながる設計」...
