SNSと自社サイト、役割を分けて効果を高める活用設計
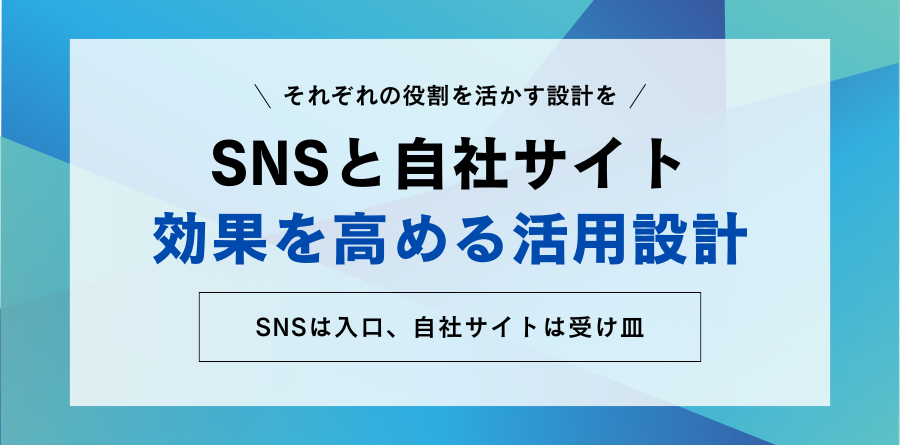
SNSと自社サイト、それぞれの役割を活かす設計を
SNSを運用している企業は年々増えていますが、「SNSだけ」あるいは「とりあえず作ったWebサイトがあるだけ」といった片側だけの運用になっているケースも少なくありません。SNSとWebサイトはどちらかが優れているという話ではなく、それぞれに異なる特性と強みがあります。
重要なのは、役割を分けて活用すること。そのうえで、ユーザーの流れを設計し、両者をうまく連携させることで、情報発信の効率やコンバージョンの成果が大きく変わってきます。
自社サイトとSNSの違い:それぞれの強みと限界
まずはSNSと自社サイトの特徴を整理しましょう。
SNSの特徴
- 日常的な情報発信や「人となり」が伝えやすく、親しみを持たれやすい
- フォロワーに継続的にリーチできる仕組みがある
- 拡散性が高く、偶然の出会いや共感を生みやすい
一方で、情報が蓄積されにくく、投稿が流れていってしまうという面もあります。また、検索に強くないため、「調べて探しに来る人」に届きづらいという弱点もあります。
自社サイトの特徴
- 情報が整理されて蓄積されるため、必要な情報にアクセスしやすい
- 検索経由で新規ユーザーの流入が見込める
- お問い合わせや資料請求など、具体的なアクションにつなげやすい
ただし、日常的な更新や、ラフな雰囲気の発信は苦手な面もあります。更新が止まってしまうと「動いていない会社」に見えてしまうリスクもあります。
主要SNSの特徴とサイト連携のポイント
Facebook:ターゲットを絞ったコミュニティ形成に強み
Facebookは日本でも一定の利用者層が存在し、特に30代以上のビジネスパーソンや地域コミュニティで根強い人気があります。自社サイトのブログ記事やイベント情報をFacebookページでシェアすることで、見込み客や既存顧客と継続的にコミュニケーションを取れます。広告機能も充実しているため、興味関心に基づいたターゲティングが可能です。
Instagram:ビジュアル訴求に優れた若年層へのアプローチ
Instagramは写真や動画を活用した直感的な魅力伝達が得意で、若年層や女性層へのアプローチに向いています。商品やサービスの使用シーンを視覚的に表現し、興味を引く投稿が効果的です。自社サイトのキャンペーンページやECページへのリンクをストーリーズやプロフィールに配置し、自然な流入を作る工夫が求められます。
Twitter:リアルタイムな情報発信と顧客対応に有効
Twitterは拡散力が高く、時事ネタや最新情報の拡散に優れています。トレンドに絡めた投稿やキャンペーン告知、顧客からの問い合わせ対応に適しています。自社サイトのニュースリリースやブログ更新情報をツイートすることで、関心を持ったユーザーをサイトへ誘導しやすくなります。
YouTube:動画コンテンツでブランドの深い理解を促進
YouTubeは動画を活用して商品の使い方や企業のストーリーを深く伝えるのに最適です。特に商品説明や導入事例、社内の様子などのコンテンツはサイト訪問者の信頼獲得に繋がります。動画を自社サイトに埋め込むことで滞在時間の向上も期待できます。
LINE:日本国内で圧倒的なユーザー基盤を活かした顧客コミュニケーション
LINEは日本で最も利用されているメッセージングアプリであり、幅広い年代層が日常的に使用しています。ビジネスアカウント(公式アカウント)を活用することで、ユーザーと直接やり取りを行い、クーポン配布やキャンペーン通知、問い合わせ対応が可能です。
特に美容院や飲食店などのサービス業では、LINEを通じて予約受付を完結させるケースが増えています。自社サイトからLINEへのリンクを設置し、ユーザーが気軽に問い合わせや予約ができる導線を作ることで、コンバージョン率の向上が期待できます。
また、LINEの強みは1対1のコミュニケーションが可能な点にあり、顧客満足度を高めるツールとしても有効です。サイトとLINEを連携させて、顧客との接点を増やしましょう。
活用のポイント:SNSは入口、自社サイトは受け皿
SNSの発信を通じて認知を広げ、共感を生み、関心を持ったユーザーを自社サイトへと誘導する。この流れを意識した設計がポイントです。
サイトへどう誘導するか
SNSの投稿で、サイト内の特集ページや事例紹介、キャンペーンページなどを紹介することで、「もっと詳しく知りたい」というユーザーを自然にサイトへ誘導できます。
特にX(旧Twitter)やInstagramのようなSNSでは、1投稿で伝えられる情報が限られるため、興味を持った人が「続きを知りたい」と思ったときにサイトへ進める導線が必要です。
サイト側でも「SNSから来た人」への配慮を
SNSから訪問したユーザーは、初めて自社を知る人が多い傾向があります。そのため、受け皿となるサイトのページでは、自己紹介やサービス内容の説明など、「初めて見る人でも分かる」構成が必要です。
また、スマートフォンからの流入が中心になるため、モバイルでの閲覧しやすさや読みやすさも重要になります。
リスクを避けつつ、信頼される発信を意識する
SNSは気軽に発信できる一方で、発言が意図しない形で広がったり、批判を受けたりすることもあります。特に言葉の選び方や時期によっては、炎上につながるリスクもゼロではありません。
とはいえ、こうしたリスクを恐れすぎて無難な投稿ばかりになると、共感や親しみは生まれにくくなってしまいます。大切なのは、「誰に、何を、どんな温度感で伝えるか」を丁寧に考えること。
自分たちの価値観や想いを言葉にして届ける姿勢が、他社との差別化やファンとの信頼構築にもつながります。単なる情報発信にとどまらず、人間らしさを感じてもらえる発信を意識してみましょう。
SNSに頼りすぎない設計を
SNSは手軽に始められる反面、継続的に運用するにはリソースや戦略が必要です。「更新が止まったSNSアカウント」が残っていると、かえって印象が悪くなってしまうこともあります。
一方、Webサイトは比較的メンテナンスの手間が少なく、情報の整理と信頼感の演出に強みがあります。SNSが止まってしまっても、しっかり整備されたWebサイトがあれば最低限の土台として機能します。
「SNSだけ」「サイトだけ」ではなく、両方の役割を把握した上で、現実的に続けられる運用体制を考えていくことが大切です。
まとめ:目的を分けて、流れをつくる
- SNSは親しみやすさや拡散に強いが、蓄積性や検索性には弱い
- 自社サイトは信頼感や情報整理に強く、問い合わせ導線をつくりやすい
- SNSで興味を持った人を、自社サイトへスムーズに誘導できるよう設計する
- 「SNS→Webサイト→アクション」という流れを意識すると、施策がつながりやすくなる
自社のリソースや運用体制に合わせて、無理なく続けられる方法を検討しながら、サイトとSNSをうまく組み合わせて活用していきましょう。
日々の更新作業や保守管理のアウトソーシングをご検討の方は、ぜひ一度ご相談ください。
無料相談はこちらから
関連サービス:大阪のホームページ運用代行・保守管理

この記事を書いた人
大阪市中央区にて2009年よりWeb制作・運用支援を行い、1,000件以上の実績を持つWeb制作会社「digrart(ディグラート)」編集部が、本記事を執筆・監修しています。
現場で培った豊富な知見を活かし、Webサイト制作、ECサイト制作、SEO対策、Webコンサルティングの実践的なハウツーをお届けします。
初心者からプロまで、Web戦略の成功をサポートする実務ベースの情報が満載です。
関連記事
-
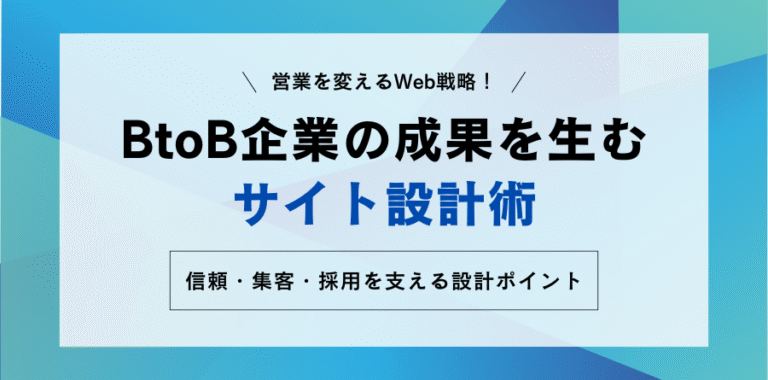
BtoB企業こそWebサイトを活用すべき理由|成果を出すコーポレートサイト設計のポイント
BtoB企業の多くは、「営業が主力だからWebサイトは補助的な役割でいい」と考えがちです。 しかし、現在では商談の約7割が営業接触前にWeb上で完了していると...
-
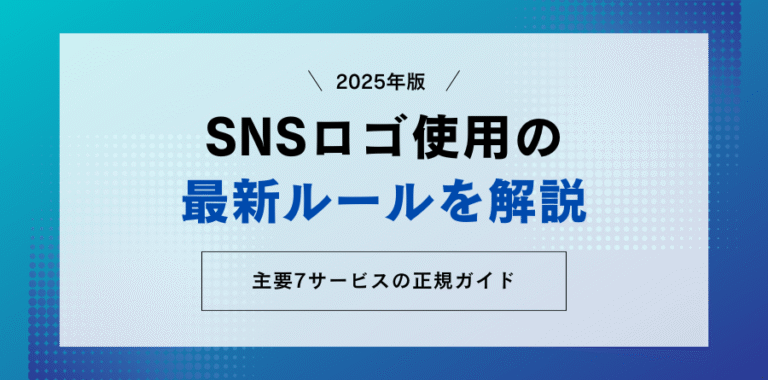
【2025年最新版】主要SNSアイコンの正しい使い方ガイド
SNSアイコンをサイトに載せてリンクを貼るのはよくあることですが、意外と知られていないのが「公式が指定する使い方を守る必要がある」ということ。 フリー素材サイ...
-
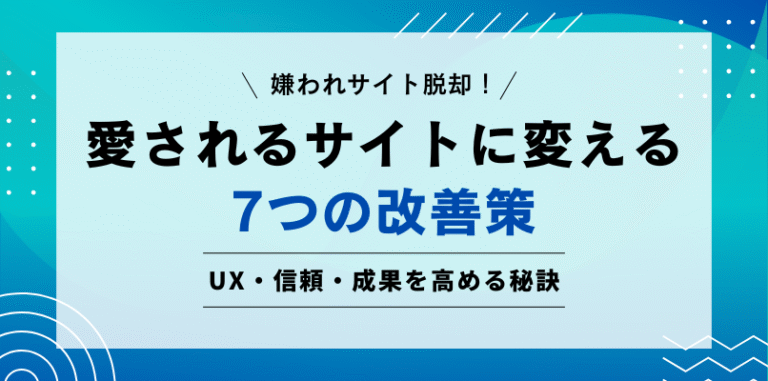
ユーザーに愛されるウェブサイトの作り方 信頼と快適さを築くための7つの要素
ウェブサイトは、ユーザーとの最初の出会いの場であり、あなたのビジネスの顔です。しかし、知らず知らずのうちに、ユーザーに「嫌われる」サイトになってしまっているかも...
