ユーザーに愛されるウェブサイトの作り方 信頼と快適さを築くための7つの要素
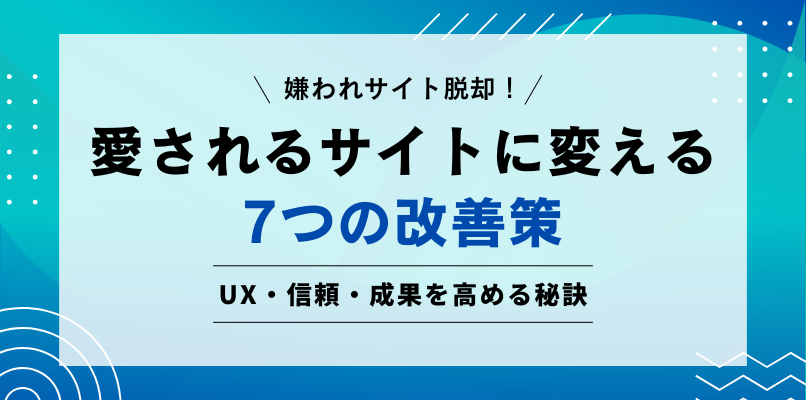
ウェブサイトは、ユーザーとの最初の出会いの場であり、あなたのビジネスの顔です。しかし、知らず知らずのうちに、ユーザーに「嫌われる」サイトになってしまっているかもしれません。
「表示が遅くて、すぐに閉じてしまった」
「どこに何があるか分からず、イライラした」
「このサイト、なんだか信用できないな」
というような体験はあなたも覚えがあるのではないでしょうか。そういったサイトにならないために、本記事では、ユーザーに嫌われるサイトにありがちな7つの特徴を解説します。これらの「嫌われるポイント」を理解し、あなたのウェブサイトをユーザーから愛される存在へと変えていきましょう。
快適な動作とスムーズな体験を提供する
ウェブサイトの基本は、ストレスなく利用できることです。ページの読み込みが遅かったり、動作が不安定だったりすると、ユーザーはすぐに離れてしまいます。快適な体験は、単なる好印象のためだけでなく、ビジネスの成果に直結する重要な要素なのです。
避けるべきこと
- ページの読み込み速度が極端に遅い
- 画像や動画のサイズが最適化されておらず、ページが表示されるまでに数秒以上かかります。ページの表示速度が1秒から3秒に遅くなるだけで、離脱率は32%増加します。さらに5秒まで遅くなると、離脱する可能性は90%にも跳ね上がります。たった1秒の遅れがコンバージョン率を7%低下させるというデータもあり、これは売り上げに直接的な打撃を与えます。
- スマートフォンに最適化されていない
- PC画面をそのまま縮小したようなデザインで、文字が読みにくく、ボタンが小さすぎます。現在ウェブサイトへのアクセスの60%以上がモバイルデバイスから行われています。モバイルに最適化されていないサイトは、この大多数のユーザーを最初から失っていることになります。
- 不意の動作や操作性の悪さ
- 自動で音楽が再生されたり、ボタンが押しても反応しなかったりします。不快な体験をしたユーザーの79%は、そのサイトで再度利用する可能性が低くなると回答しており、リピーターを育てる上でもスムーズな動作は不可欠です。
実践すべきこと
- 読み込み速度を高速化する
- 画像の圧縮、不要なスクリプトの削除、キャッシュの活用など、技術的な対策を講じ、表示速度を1秒以内に近づけましょう。ページの表示が1秒遅れるごとに、コンバージョン率が7%低下するというデータは無視できません。高速化は単なる技術的な課題ではなく、直接的な収益の向上につながる最優先事項です。
- モバイルファーストで設計する
- レスポンシブデザインを導入し、どのデバイスからアクセスしても快適に閲覧できるよう工夫しましょう。ウェブサイトへのアクセスの60%以上はモバイルデバイスからです。モバイルユーザーがスムーズに操作できるサイトは、ユーザーの満足度を高めるだけでなく、Googleからの評価も向上し、検索順位にも良い影響を与えます。
- ユーザーの操作を尊重する
- ユーザーの許可なく何かを始めたり、邪魔をしたりするような要素は排除しましょう。自動再生される動画やポップアップ広告は、ユーザーの体験を著しく損ない、不快な体験をしたユーザーの79%は、そのサイトで再度利用する可能性が低くなると回答しています。ユーザーが主導権を持ってサイトを利用できるよう、クリーンでシンプルなデザインを心がけましょう。
情報を整理し、分かりやすく伝える
ユーザーは目的の情報を見つけるためにサイトを訪れます。情報が散らかっていたり、分かりにくい言葉が使われていたりすると、ユーザーは混乱してしまいます。
避けるべきこと
- 同じ情報が複数のページに重複している
- サービス内容や料金表など、同じ内容が複数のページに掲載されていると、ユーザーは何度も同じ情報を見ることになり時間のロスに繋がります。また、内容に修正があった場合には複個所を修正する必要があり、管理上の複雑さも増え、更新漏れ等あった場合にはさらにユーザーを混乱させてしまう事になります。情報の重複は検索エンジンからも好まれませんので、その点からも避けるべき事項です。
- 専門用語を多用する
- 「コンピテンシー」「シナジー」といった、特定の業界でしか通じない言葉をメニューや見出しに使う。これにより、ユーザーはサイトの内容を正確に理解できず、結果として目的の情報を得られないまま離脱してしまいます。ターゲットとなるユーザー層が専門家でない場合は、特に注意が必要です。
- 情報の階層が深すぎる
- 目的のページにたどり着くまでに何度もクリックが必要で、ユーザーが途中で面倒になってしまいます。サイト内を検索する手間や、何度クリックしても辿り着けないという不満は、ユーザーの集中力を奪い、離脱の大きな要因となります。
実践すべきこと
- 情報を一元化する
- 特定の情報は一つのページに集約し、他のページからはリンクで誘導するようにしましょう。これにより、ユーザーは最新かつ正確な情報を得られるようになり、サイトの信頼性が向上します。また、管理の手間も軽減され、更新ミスを防ぐことにもつながります。
- 平易で直感的な言葉を使う
- 誰にでも理解できる言葉を選び、分かりやすい表現を心がけましょう。見出しやメニュー項目は、ユーザーが「ここに欲しい情報がある」と直感的に判断できる言葉を選ぶことが重要です。
- 階層を浅くする
- 主要なコンテンツには、トップページから2〜3クリックでアクセスできるように設計しましょう。多くのユーザーは、3回以上クリックしても目的の情報にたどり着けない場合、サイトへの関心を失う傾向があります。パンくずリスト(現在地を示すナビゲーション)を設置し、ユーザーがサイト内で迷わないように配慮することも効果的です。
承知いたしました。「優れたナビゲーションでユーザーを導く」セクションに、より具体的で説得力のある情報を追加し、ボリュームを増やします。
優れたナビゲーションでユーザーを導く
ナビゲーションはサイトの「地図」です。それが使いにくいと、ユーザーは迷子になり、不満を感じてしまいます。ユーザーを適切に案内するナビゲーションは、サイトの信頼性を高め、スムーズなサイト回遊を促す上で非常に重要です。
避けるべきこと
- メニューが分かりにくい
- どこに何があるか分からなかったり、メニューが隠されていたりする。特にデスクトップ版でハンバーガーメニューのみを設置するのは避けるべきです。PCでは画面サイズが広いため主要なメニュー項目は常に表示しておく事がでるため、多くの場合ではクリックというワンステップを踏まなければならないハンバガーメニューを設置する必要はありません。一方、スマートフォンの場合は画面が小さいためハンバーガーメニューは有効ですが、多くのユーザーが右手の親指で操作しているため、ハンバーガーメニューは右上に設置するのが好ましいとされています。
- 見出しと内容の不一致
- メニューの文言と遷移先のページのタイトルが異なり、ユーザーが「別のページに来てしまった」と混乱する。例えば、メニューで「サービス」と表示されているのにクリックすると「料金プラン」のページに飛ぶなど、ユーザーの期待と実際の挙動が一致しないケースです。これはユーザーの信頼を大きく損なう行為であり、求めている情報を見つけられないと感じたユーザーは、すぐにサイトを離れてしまうでしょう。
- 外部リンクの混在
- サイト内のリンクと外部サイトへのリンクが混在しており、ユーザーが予期せず別のサイトへ移動してしまう。これにより、ユーザーはサイト内での回遊を中断され、元のサイトに戻る手間を強いられます。特に、ユーザーに事前に警告することなく新しいタブで開かない場合、ユーザーはサイトに戻るのが面倒になり、そのまま離脱する可能性が高まります。
- リンクだと分かりにくいデザイン
- クリックできるのかどうかが一見して分からず、ユーザーが迷ってしまう。リンクには、下線や色の変化、マウスオーバー時のエフェクトなど、視覚的に「クリックできる」ことが明確に分かるデザインが必要です。 ユーザーは、クリックできる場所を探すことに時間を費やしたくありません。
実践すべきこと
- 直感的で一貫性のあるメニューを配置する
- サイト全体で同じ場所に、同じ構成でメニューを表示しましょう。特にデスクトップ版では、主要なナビゲーションを常時表示させるのが効果的です。これにより、ユーザーはサイト内での現在地を把握しやすくなり、スムーズな回遊体験が実現します。
- パンくずリストで現在地を示す
- ユーザーがサイト内のどこにいるのかを常に示し、安心してサイト内を回遊できるようにしましょう。パンくずリストは、ユーザーが前の階層に戻りたいときに役立つだけでなく、サイトの構造を理解する上でも重要な役割を果たします。
- リンクの遷移先を明確にする
- メニューの文言と遷移先のページ内容を一致させ、ユーザーの期待を裏切らないようにしましょう。外部サイトへのリンクには、外部リンクであることを示すアイコン(例:外部サイトアイコン)を付けると親切です。これにより、ユーザーは安心してリンクをクリックできます。
- クリックできることが明確なデザインにする
- マウスオーバーで色が変わる、下線が付くなど、視覚的にクリックできることが伝わるように工夫しましょう。クリックできる要素とそうでない要素を明確に区別することは、ユーザーのサイト利用におけるストレスを大幅に軽減します。
信頼性を築き、安心感を与える
ユーザーは、信頼できるサイトでなければ、個人情報の入力や購入といった行動を起こしません。特に、ECサイトや会員登録が必要なサイトでは、ユーザーに「このサイトは安全だ」という確信を与えることが不可欠です。
避けるべきこと
- 運営者情報が不確か
- 会社概要やプライバシーポリシー、連絡先などが明確に記載されていない。特定商取引法に基づく表記がない場合は、法律違反になる可能性もあります。ユーザーは、問題が発生した際にどこに連絡すれば良いか分からず、不安を感じてしまいます。
- しつこいポップアップ広告
- コンテンツを覆い隠すような大きな広告が頻繁に表示される。コンテンツを閲覧する邪魔になる広告は、ユーザーを苛立たせ、サイトへの不信感につながります。 特にモバイルでは、画面の大半を占める広告はユーザー体験を著しく損ないます。
- セキュリティの不安
- URLが「http」のままであったり、セキュリティに関する情報が不足していたりする。現代のブラウザは、HTTPS化されていないサイトに「安全ではありません」といった警告を表示します。この警告は、ユーザーの不安をあおり、サイトを離れる原因となります。
実践すべきこと
- 運営者情報を明確に記載する
- 会社概要、プライバシーポリシー、問い合わせ先などを分かりやすい場所に配置しましょう。特に、特定商取引法に基づく表記やプライバシーポリシーは、フッターなどの全ページからアクセスできる場所にリンクを設置するのが一般的です。 また、担当者名や事業責任者の氏名まで記載することで、より透明性を高めることができます。
- ユーザー体験を優先する
- ユーザーの行動を邪魔するような広告は避け、コンテンツを快適に閲覧できる環境を提供しましょう。ポップアップを完全に無くすことが難しい場合でも、ユーザーがすぐに閉じられるようにバツボタンを大きくする、スクロールに追従しないようにするなどの配慮が重要です。
- セキュリティを強化する
- SSL(HTTPS)を導入し、ユーザーが安心してサイトを利用できる環境を整えましょう。SSL化は、Googleも検索順位の評価項目の一つとしているため、SEOの観点からも重要です。また、ログインや個人情報の入力フォームがあるページでは、セキュリティ証明書(例: Comodo, DigiCertなど)のロゴを掲載することも、ユーザーに安心感を与えます。
ユーザーの意図しない挙動や強制的な動作をなくす
ユーザーは、自分の操作がコントロールできなくなると、強い不快感や不信感を抱きます。ウェブサイトは、訪問者の自由な行動を尊重すべきです。
避けるべきこと
- 自動再生される動画や音声
- ユーザーの許可なく、コンテンツが再生され、不意に大きな音が出ます。これはユーザーの作業を中断させ、不快な体験を与える最も一般的な例です。特にモバイルユーザーは、公共の場所で突然大きな音が出ることによるストレスを感じやすくなります。
- 予測不能なレイアウトの崩れ
- ページの読み込み中にコンテンツがガタガタと動き、ユーザーがクリックしようとしたボタンが突然別の場所に移動してしまう。これは広告や画像の遅延読み込みで起こりやすく、ユーザーの意図しないクリックや誤操作を引き起こします。
- フォームの煩雑さ
- フォームの入力項目が多すぎたり、スマートフォンでの入力時に不適切なキーボードが表示されたりすると、ユーザーは面倒に感じて途中で入力を諦めてしまいます。入力項目が不必要に多い場合や、電話番号入力欄で文字キーボードが表示される場合など、ユーザーに余計な手間をかけると、コンバージョンが低下する恐れがあります。
実践すべきこと
- ユーザーの行動を第一に考える
- 動画や音声は、クリックしてから再生されるようにしましょう。これにより、ユーザーは自分のタイミングでコンテンツを消費することができます。また、大きな動画を配置する場合は、あらかじめミュートにしておく、あるいは再生・停止ボタンを分かりやすく配置するなどの配慮も重要です。
- コンテンツの安定性を確保する
- ページの読み込みが完了するまで、レイアウトが動かないように工夫しましょう。特に広告や動的なコンテンツの表示エリアは、あらかじめスペースを確保しておくことで、後からコンテンツが読み込まれても他の要素がずれることを防げます。
- フォームを適切に設計する
- 入力項目は必要最小限に抑え、ユーザーが迷わずに入力完了できるようにしましょう。電話番号の入力欄には「tel」属性を設定するなど、入力内容に適したキーボードが自動で表示されるように実装することが大切です。これにより、入力の手間を減らすだけでなく、ユーザーにストレスのない体験を提供できます。
コンテンツの不透明さや情報の隠蔽をなくす
ユーザーは、情報が隠されていると感じると、サイトの信頼性を疑います。特に、購入やサービスの利用に関わる重要な情報は、透明性を確保する必要があります。
避けるべきこと
- 価格情報が不明確
- 製品やサービスの料金が記載されておらず、問い合わせが必要になる。ユーザーは価格が不透明なサイトに対し、不信感を抱きます。特に、他サイトでは価格が明示されている場合、ユーザーは「何か隠しているのでは?」と感じて、競合サイトに流れてしまう可能性が高まります。
- 運営者情報が不足している
- 会社概要や責任者の名前、住所、電話番号などが明確に記載されていない。これは、「誰が運営しているか分からない」という不安をユーザーに与えます。特に、ECサイトや有料サービスを扱うサイトでは、特定商取引法により、運営者情報(氏名、住所、電話番号)の明記が義務付けられています。これがない場合は法律違反となる可能性があります。
- 問い合わせ方法が複雑
- 連絡先がフォームしかない、電話番号がない、返信が遅いなど、問題発生時の連絡手段が不確か。ユーザーは何か困ったことがあったときに、すぐに連絡が取れるかという点でサイトを評価します。 連絡先が分かりにくいと、「このサイトはトラブルに対応してくれないかもしれない」という不安につながり、購入や利用をためらいます。
実践すべきこと
- 価格を明確に提示する
- 料金プランや価格表は、ユーザーがアクセスしやすい場所に明記しましょう。追加費用やオプション料金がある場合は、それも分かりやすく記載することが重要です。 全ての費用を事前に公開することで、ユーザーは安心して検討を進められます。
- 運営者情報を充実させる
- 企業情報、連絡先、プライバシーポリシーなどを分かりやすい場所に記載し、サイトの透明性を高めましょう。フッターにこれらの情報へのリンクを配置することは、サイト全体の信頼性を高める上で非常に有効な手段です。
- 複数の問い合わせ方法を提供する
- メールフォームだけでなく、電話番号やチャットボットなど、複数の問い合わせ手段を用意しましょう。ユーザーはそれぞれ異なる状況やニーズを持っています。 複数の選択肢を提供することで、ユーザーは自分に最も適した方法で連絡を取ることができ、サイトへの満足度が向上します。
明確な「行動の呼びかけ」を設ける
ユーザーに「次に何をしてほしいか」を明確に示さないと、ユーザーは次に何をして良いか分からず、サイトを離れてしまいます。明確な「行動の呼びかけ」(CTA:Call to Action)は、ユーザーを次のステップへとスムーズに導き、サイトのコンバージョン率を向上させるために不可欠な要素です。
避けるべきこと
- 行動を促すボタンがない
- サービス紹介のページに、「申し込み」や「問い合わせ」のボタンがない。ユーザーは、コンテンツを読み終えた後に「次に何をすればいいのだろう?」と迷ってしまいます。行動への明確な導線がないと、せっかく興味を持ったユーザーも、どう行動していいか分からずに離脱してしまいます。
- ボタンの文言が不明確
- 「こちら」や「詳細」といった、抽象的でクリックをためらわせる文言を使う。ユーザーはクリックする前に、そのボタンが何をもたらすかを予測したいと考えます。不明確な文言は、ユーザーに「このボタンを押すとどうなる?」という疑問を抱かせ、行動を躊躇させる原因となります。
- 行動の導線が複数ありすぎる
- ユーザーを誘導したい行動が複数あり、それぞれが競合している。一つのページに「資料請求」と「無料相談」と「今すぐ購入」のボタンが並んでいると、ユーザーはどれを選べばいいか分からず混乱します。選択肢が多すぎると、ユーザーは最終的に何も選択しない「決断麻痺」の状態に陥りがちです。
実践すべきこと
- 明確なCTA(Call to Action)ボタンを設置する
- 「無料で試す」「今すぐ購入する」「資料請求」など、具体的で分かりやすい文言を使いましょう。CTAボタンは、ユーザーがコンテンツを読み終えた後や、ページの重要な箇所に、複数回配置するのが効果的です。これにより、ユーザーはいつでも次の行動に移ることができます。
- CTAを目立たせる
- ボタンの色を背景と異なる色にするなど、視覚的に目立たせましょう。人間の視線は、コントラストが強く、目立つ色に引き寄せられる傾向があります。 ボタンの大きさや配置も工夫し、一目で「クリックできる」と認識させることが重要です。ただ目立たせる事だけに注視して、デザイン性やユーザーの快適性を損なう事が無いように注意が必要です。
- 導線をシンプルにする
- ユーザーに取ってほしい行動を一つに絞り込み、迷わないように誘導しましょう。一つのページにつき、主要なCTAは一つに絞るのが原則です。 複数のボタンを配置する場合でも、メインのCTAを最も目立たせ、サブのCTAは控えめにするなどの優先順位をつけましょう。
ユーザー体験(UX)というのはサイト制作において非常に重要なポイントです。ユーザーがストレスを感じれば離脱率の増加やコンバージョンの低下に繋がり、ユーザー行動が良くなければ検索エンジンの評価も下がり、ユーザー数自体が減るという悪循環に陥ります。
これらの点を改善することにより、ユーザーに愛されるサイトになるでしょう。

この記事を書いた人
大阪市中央区にて2009年よりWeb制作・運用支援を行い、1,000件以上の実績を持つWeb制作会社「digrart(ディグラート)」編集部が、本記事を執筆・監修しています。
現場で培った豊富な知見を活かし、Webサイト制作、ECサイト制作、SEO対策、Webコンサルティングの実践的なハウツーをお届けします。
初心者からプロまで、Web戦略の成功をサポートする実務ベースの情報が満載です。
