実店舗連動ECの設計|在庫・POS連携のチェックリスト
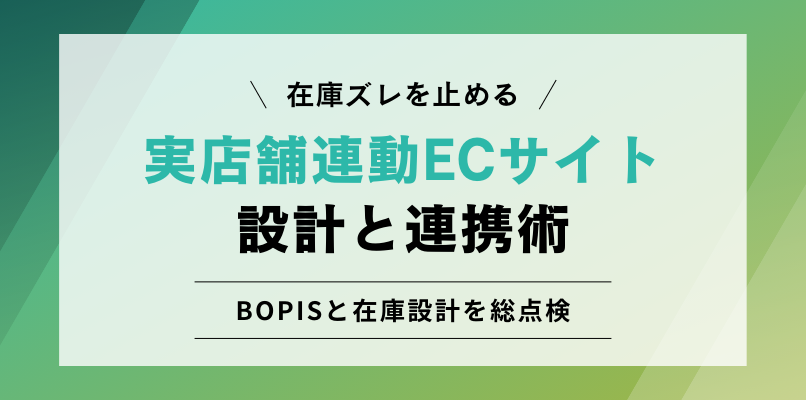
「ECと店舗の在庫が合わない」「店頭受け取りで現場が混乱」——多くは在庫の一元管理とイベント設計(予約・引当・取り置き)の不足が原因です。商品IDの突合・ロケーション管理・引当タイミング・店舗オペを先に決めれば、BOPIS(店頭受け取り)や在庫可視化は安定します。本稿は設計原則 → 実装パターン → チェックリストで、迷いどころを具体化します。
まず決めるべきこと:在庫の持ち方と引当のルール
はじめに在庫の“見え方”と“減り方”を定義します。単一在庫プールでロケーション別に配分するか、店舗ごとに完全分離するか、あるいはOMSでハブ化するか。引当タイミングは注文時/決済時/店舗確保完了時のどれかを選びます。店頭受け取り(BOPIS)は店舗での準備 → 受け渡し → 完了処理までが一連の体験。ここを設計書に落とし込むと現場の迷いが激減します。
実装パターンの比較(在庫の持ち方)
| パターン | 概要 | 向き/強み | 注意点 |
|---|---|---|---|
| A:単一在庫プール+ロケーション別数量 | 1商品に複数ロケーション数量を保持 | EC/店舗の一体運用が容易 | ロケーションID管理が必須(API・権限 |
| B:店舗別在庫の完全分離 | 店舗=在庫の最小単位 | 店舗裁量が大きい | 跨店の引当/移動に運用負荷 |
| C:OMS中継(在庫ハブ) | OMSが注文振り分け/引当 | ルール柔軟・拡張に強い | 初期コスト/設計が増える |
引当(予約)設計のポイント
- いつ在庫を減らすか(注文時/決済時/店舗確保時)を明確化
- 安全在庫(バッファ)と引当有効期限(〇分)を設定
- 取り置き失効 → 自動在庫戻し/通知フローを用意
BOPIS運用は「準備 → 通知 → 受け取り → 完了」の明確化が肝です。
データ設計:IDの突合とロケーション・SKU管理
EC×POS連携の失敗はIDの不一致から生まれます。まずSKU(社内ID)を主軸に、GTIN/JANなどの標準コードを紐づけ、バリエーション(色/サイズ)を持てるスキーマに。ロケーションは店舗・倉庫・EC倉庫を一意に識別し、棚卸や移動在庫も数量として扱える設計が安定します。Googleのローカル在庫広告を視野に入れる場合は、商品・在庫のローカルフィードも想定しましょう。
突合テーブルの基本(例)
- product_id(社内) / sku / variant_id
- gtin_jan(GTIN-13) / brand / category
- location_id(店舗/倉庫) / qty_on_hand / qty_reserved
- updated_at(POS側/EC側) / source_system
GTIN(JAN/EAN/UPC等)はGS1標準。店舗・倉庫での管理や外部配信(LIAなど)の基礎になります。
BOPIS/店舗受け取りの設計:フローと通知
BOPISは注文 → 引当 → 準備 → 通知 → 受け渡し → 完了のオペレーションが要です。EC側は受け取り場所の選択と引当ロジック、店舗側は準備リストと通知、引き渡し時は本人確認/検品/在庫確定をUIで支援。Shopify POSなどは店頭受け取りのステータス管理と通知が標準化されています。
必須UI/運用
- 店舗準備リスト:優先度(受取期限/在庫確保状況)で並び替え
- 通知:準備完了・期限切れ・キャンセルの自動通知
- 受け渡し:本人確認(注文番号/バーコード) → 完了処理で在庫確定
KPI例
- 準備リードタイム(注文 → 準備完了)
- 受取完了率/期限切れ率
- 受取時の追加購買率(BOPISは追加購買が起きやすい傾向)
連携方式の選択:API/バッチ/ミドルの使い分け
リアルタイム性と安定性はトレードオフです。API連携は鮮度に強い一方、リトライ/制限設計が必須。バッチ連携は堅実だが鮮度が落ちます。ミドル(OMS/在庫ハブ)はルールの柔軟性と監査性を確保しやすい反面、初期設計が増えます。POSはスマレジ等で在庫・受注系APIが公開されており、要件別に選び分けます
比較表(方式別)
| 方式 | 強み | 弱み | こんな時に |
|---|---|---|---|
| API(双方向) | 鮮度◎/イベント駆動 | 失敗時の再送/冪等性が必須 | BOPISや店舗在庫表示をほぼ実時間で出したい |
| バッチ(CSV/Feed) | 安定/監査しやすい | 鮮度△ | 1日数回の在庫反映で十分 |
| ミドル(OMS) | ルール柔軟/監視◎ | 初期工数 | 複数倉庫・複数チャネルを最適配分したい |
セキュリティと決済の前提(要点だけ)
店舗×ECの連携ではカード情報の取り扱いを極力避ける設計が基本。トークン/外部決済でPCI DSSのスコープを縮小します。POSやEC間の通信はAPIキー/署名・IP制限で守り、ログ監査を残すこと。
最低限の実務
- カード情報は保存しない(トークン化/代行)
- 管理画面・APIは二段階認証/IP制限
- 監査ログ(誰が/いつ/何を)を保存
実装チェックリスト(保存版|在庫・POS連携)
要件定義〜公開前に“欠けやすい”ポイントを横断で点検できます。在庫の見せ方・減らし方・戻し方と、BOPIS運用、連携の堅牢性を一括で確認。現場配布用にExcel版へも展開可能です。
要件・データ
- SKU ⇔ GTIN/JANの突合表を作成・共有(棚卸/外部配信も想定)
- location_id(店舗/倉庫)を一意管理/ロケーション在庫API方針を決定
- 予約在庫(qty_reserved)と安全在庫の閾値を設定
在庫の減り方/戻し方
- 引当タイミング(注文/決済/準備完了)を合意
- 取り置き失効 → 自動戻し/通知のシナリオ化
- 返品・キャンセルの在庫戻しと期限を定義
BOPIS運用
- 店舗準備リスト → 準備完了通知 → 受け渡し → 完了処理の一連フローをUI化
- 本人確認(注文番号/バーコード)と在庫確定の手順書
- KPI:準備LT/受取完了率/期限切れ率/追加購買率
連携・監視
- API:リトライ/冪等性/レート制御/バッチ:再実行/差分
- 障害時の降格運転(在庫表示を“お取り寄せ”へ等)
- 監査ログと通知(在庫ズレ閾値)の設定
事例に学ぶ:小売の“店頭受け取り”が効く理由
BOPISは受取来店時の追加購買と配送コスト削減が同時に狙える施策。統計でも、受取時に追加購入が生まれやすいと報告されています。まずは受取体験の摩擦(待ち時間・導線・確認)を下げ、受取場所のPOPや関連導線を設計すると、売上の底上げが期待できます。
よくある質問(FAQ)
Q1:在庫は注文時と決済時のどちらで引き当てるべき?
A. 迷ったら注文時に仮押さえ → 期限切れで戻すが無難です。決済前に在庫が消える事故を抑えられます。BOPISでは店舗確保完了で本確定にする運用も多いです。
Q2:店頭受け取りで一番揉めるのは?
A. 準備完了・期限切れの通知不足と、受け渡し時の本人確認ミスです。POS/ECの通知機能を必ず使い、完了処理で在庫を確定させましょう。
Q3:まず小さく始めたい。API連携は必須?
A. 需要次第ですが、バッチ(1日数回)から開始 → 要件固まり次第APIが現実的です。スマレジ等はAPIが整っているので、将来拡張を考えている方にはおすすめです。
Q4:商品コードはJANだけでいい?
A. SKU(社内ID)+GTIN/JANの二段構えが安全です。棚卸・外部配信・連携時の照合精度が上がります。
Q5:店舗在庫を広告にも活かせる?
A. Googleローカル在庫広告(LIA)で店舗別在庫を露出できます。Merchant CenterとBusiness Profileの連携が前提です。
まとめ
在庫が“どこで・どう減って・いつ戻るか”を先に決め、ID突合・ロケーション管理・BOPIS運用を設計書に落とし込めば、店舗連動ECは安定します。最初はシンプルに始め、通知・監視・ロールバックを備え、LIAなど集客との接続まで見据えると効果が長持ちします。
大阪でECサイトの構築やリニューアルをご検討の方は、ぜひ一度ご相談ください。
無料相談はこちらから
関連サービス:大阪のECサイト制作・構築

この記事を書いた人
大阪市中央区にて2009年よりWeb制作・運用支援を行い、1,000件以上の実績を持つWeb制作会社「digrart(ディグラート)」編集部が、本記事を執筆・監修しています。
現場で培った豊富な知見を活かし、Webサイト制作、ECサイト制作、SEO対策、Webコンサルティングの実践的なハウツーをお届けします。
初心者からプロまで、Web戦略の成功をサポートする実務ベースの情報が満載です。
関連記事
-
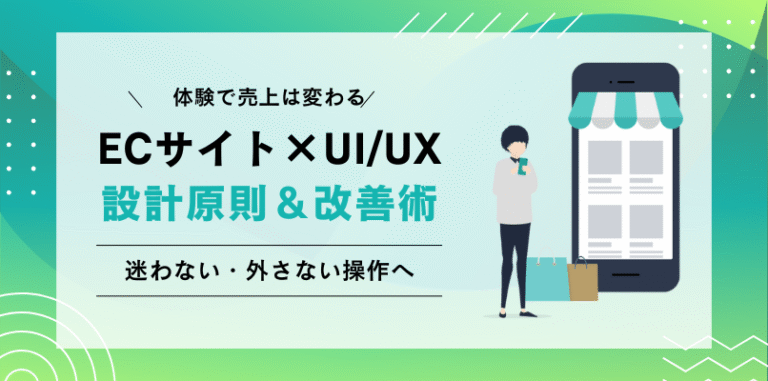
ECサイト制作×UI/UX|使いやすさを上げる設計原則と改善術
「商品は良いのに、離脱が多い」「スマホで操作しづらいと言われる」——ECの成果は、UI/UX(使いやすさ)の出来で大きく変わります。まずは普遍的な設計原則(ニー...
-

ECサイト制作×SEO|集客につながる情報設計と実装チェック
「デザインは良いのに検索から流入が伸びない…」「商品は揃っているのにカテゴリ回遊が弱い…」。ECの集客は“作る”だけでは完結せず、情報設計(IA)とSEOの実装...
-

ECカート選定の正解は?Shopify・makeshop・BASEを徹底比較
「どのカートが“うち”の正解か、決め手がない」「初期は安くても変動費で重くなるのが不安」——そんな迷いを解消するために、本記事では料金・手数料の実額と運用のしや...
