Web制作の「よくある失敗事例」10選と対策|トラブルを未然に防ぐには
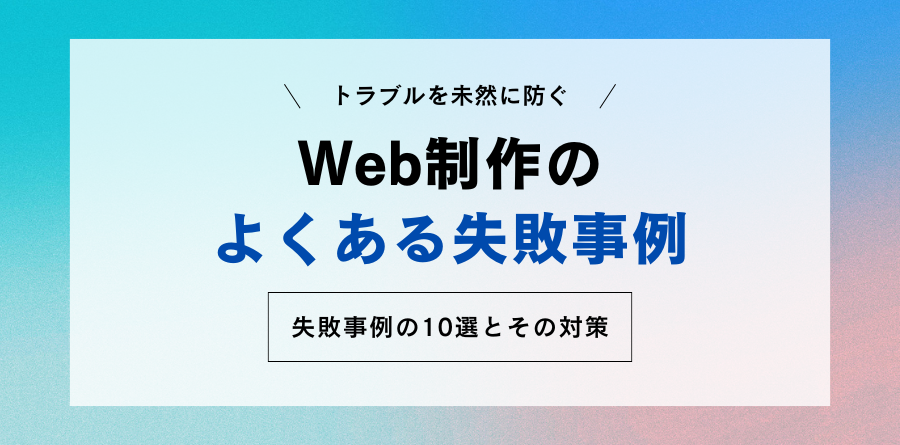
Webサイト制作において、「思っていた仕上がりと違う」「公開後に不具合が見つかる」「全然成果が出ない」などのトラブルは珍しくありません。
特に初めてのリニューアルや、社内にWeb専門の担当者がいない場合は、こうした失敗が起きやすくなります。
本記事では、Web制作でありがちな失敗パターンを10個にまとめ、それぞれの対策を紹介します。
発注側として知っておくだけで、トラブルの回避やよりよいサイトづくりにつながります。
1. ゴールが曖昧なまま制作が始まる
「とりあえず古いからリニューアルしたい」「名刺代わりにあればいい」といった抽象的な理由で進めると、目的が定まらず、制作途中で迷走しがちです。
デザインや構成に対する評価軸もブレてしまい、社内でも「良い/悪い」の判断ができなくなります。しかし、ビジネスにおけるWebサイトの重要性は年々増しています。
実際、米国の調査会社Gartner(旧CEB)の調査によると、BtoBの購買プロセスの57%は、営業担当者に接触する前に完了していると言われています。顧客はWebサイト等での情報収集段階で、すでに「ある程度の選別」を終えているのです。
出典:The B2B Buying Journey – Gartner
「とりあえず」で作ったサイトでは、この選別の土俵にすら立てない可能性があります。
【対策】具体的なKPIを設定する
Webサイトの目的を明確にし、KPIを設定してからプロジェクトを始めましょう。
- 問い合わせを増やしたい → フォームの最適化、導線強化
- 商品を販売したい → カート機能、決済の利便性向上
- 採用活動を強化したい → 会社の魅力発信、社員インタビュー
2. ターゲットユーザーの定義が不十分
「誰向けのサイトか」が曖昧なままだと、デザインやコンテンツの方向性がぶれてしまいます。
結果として、「誰にも刺さらない」無難なサイトになるケースも多く、特にBtoBでは決裁者と実務担当のニーズが混在するため、明確な棲み分けが必要です。
【対策】ペルソナを設定する
ペルソナ(架空の顧客像)を設定し、「どんな悩みを持ち、どんな情報を求めているか」を明確にしておくことで、的確な訴求が可能になります。
3. レスポンスが遅く、スケジュールが崩れる
制作中のやり取りで、顧客側のレスポンスが遅れると、プロジェクト全体のスケジュールに大きな影響が出ます。
確認や承認の遅延、追加要望への対応の遅れが重なると、納期が遅れるだけでなく、制作会社のリソース調整も困難になり、結果として品質やコスト面でのトラブルにつながりやすくなります。
【対策】確認期限を共有する
スケジュールとレスポンス期限を事前に確認し、遅れそうな場合は早めに連絡しましょう。確認事項には期限を設けてリマインドし、迅速なやり取りを心がけることが大切です。
4. コンテンツ制作を後回しにする
「デザインだけ先に作って、原稿はあとで…」という進め方は、スケジュール遅延や情報の整合性ミスにつながります。
そもそも制作会社が想定している原稿ボリュームと実際の文章量が合わず、デザインを大きく調整しなければならない手戻りが発生することもあります。
【対策】ワイヤーフレームと原稿を並行する
サイト構成(ワイヤーフレーム)と並行して原稿も作成・整理を始め、制作全体の見通しを立てることが重要です。
5. デザインにこだわりすぎて使いにくい
見た目の美しさにこだわりすぎて、情報が探しづらい、ボタンが小さいといったユーザビリティの低下が起こるケースがあります。
また、ユーザーがWebサイトのデザインを見て「好ましいか」を判断するのにかかる時間は、わずか0.05秒(50ミリ秒)だという研究結果もあります。
参考:Eye-tracking studies show first impressions form quickly – Missouri S&T
ファーストビューで迷わせてしまうデザインは、それだけで離脱の原因となります。
さらに、PCでの見た目ばかり気にして、スマホでの表示(モバイル対応)がおろそかになるのも典型的な失敗例です。総務省の「令和5年通信利用動向調査」によると、世帯におけるスマートフォンの保有割合は90.6%に達しています。
出典:令和5年通信利用動向調査の結果 – 総務省
【対策】モバイルファーストと使いやすさを優先
ユーザー目線での導線設計やアクセシビリティ(読みやすさ・使いやすさ)を優先し、バランスの取れたデザインにしましょう。必ずレスポンシブデザイン(スマホ対応)を前提に進めてください。
6. コーディング・システム構築後の大幅な修正依頼
デザイン提出段階ですり合わせを行っていても、コーディング完了後やシステムの実装後になってから「やっぱりここを変えたい」といった依頼が出てくることがあります。
内容によっては大幅な改修となり、追加見積もりが発生することも。これを巡って認識のズレが起きると、依頼主と制作会社の間にトラブルが生じやすくなります。
【対策】デザイン段階で入念にチェックする
デザインの確認段階でよく確認し、気になる点があればこの時点で必ず伝えるようにしましょう。後工程での変更はコストがかかることを意識することが大切です。
7. SEOや集客施策が後回しになっている
公開後に「検索で全然出てこない!」「誰も見に来てくれない」となるのは、SEO設計や集客計画が不十分だった典型的なパターンです。
見た目や表現を優先するあまり、キーワードが埋もれたり、ページ構造が検索エンジンに伝わりづらい作りになってしまうことも少なくありません。
【対策】企画段階から集客戦略を組み込む
キーワード選定、タイトル・見出し設計、構造化マークアップなどを、企画段階からSEOを意識して取り入れましょう。
また、SEOは効果が出るまでに時間がかかります。即効性を求めるなら、公開直後から「Web広告(リスティング広告)」や、特定のターゲットに向けた「LP(ランディングページ)」の運用も視野に入れ、多角的なアプローチで集客効果を最大化する計画を立てておきましょう。
8. 問い合わせフォームが使いにくい
フォームが長すぎたり、必須項目が多すぎると、ユーザーは途中で離脱してしまいます。
HubSpot社の調査によると、フォームの入力項目数を「4つから3つ」に減らすだけで、コンバージョン率(CVR)が約50%改善したというデータもあります。
参考:Which Types of Form Fields Lower Landing Page Conversions? – HubSpot Blog
「ユーザーの手間を一つ減らすこと」は、立派なマーケティング施策なのです。
【対策】EFO(入力フォーム最適化)を意識する
最小限の項目で完了できるフォームを設計し、入力しやすいUI(スマホ対応、プレースホルダー活用など)を意識しましょう。エラー表示のわかりやすさや、送信完了ページ(サンクスページ)の設置も忘れずに行います。
9. 社内確認フローが混乱する
確認・承認フローが不明確だと、「誰が判断するのか」「どこまで進んでいるのか」が分からなくなり、進行が滞ります。
特に部署をまたぐプロジェクトでは、関係者の意見が割れて合意形成に時間がかかり、納期に間に合わなくなるケースも見られます。
【対策】決定権を持つ人を明確にする
プロジェクト開始時に「誰が何を決めるのか」を明確にし、進捗管理ツールや定例ミーティングで状況を共有しましょう。
10. 公開後の運用・改善がされていない
せっかく作ったサイトも、更新されず放置されると、情報が古くなり、信頼性を損ないます。
古いままのスタッフ情報やイベント告知、リンク切れなどは、訪問者にマイナスの印象を与え、「この会社は本当に活動しているのか?」と疑問を持たれる原因になります。
【対策】PDCAサイクルを回す
公開後の保守・更新体制を確保し、アクセス解析やユーザーフィードバックをもとに改善を続けていくことが重要です。
アクセス解析ツール(Googleアナリティクスなど)を活用して「どのページが見られているか」「どこで離脱しているか」を分析し、コンテンツの追加やデザイン調整といった改善(PDCA)を継続的に行いましょう。
まとめ|「作って終わり」にしないために
Web制作は、単なる見た目の美しさではなく、ビジネスの成果を生み出すための“設計と運用”が求められます。
今回紹介した失敗事例と対策を事前に知っておけば、制作会社との連携もスムーズに進み、より効果的なWebサイトを構築できます。
「何を目的に、誰に届けるのか」を常に意識しながら、制作を進めていきましょう。
大阪でWebサイト制作をご検討の方は、ぜひ一度ご相談ください。
無料相談はこちらから

この記事を書いた人
大阪市中央区にて2009年よりWeb制作・運用支援を行い、1,000件以上の実績を持つWeb制作会社「digrart(ディグラート)」編集部が、本記事を執筆・監修しています。
現場で培った豊富な知見を活かし、Webサイト制作、ECサイト制作、SEO対策、Webコンサルティングの実践的なハウツーをお届けします。
初心者からプロまで、Web戦略の成功をサポートする実務ベースの情報が満載です。
関連記事
-
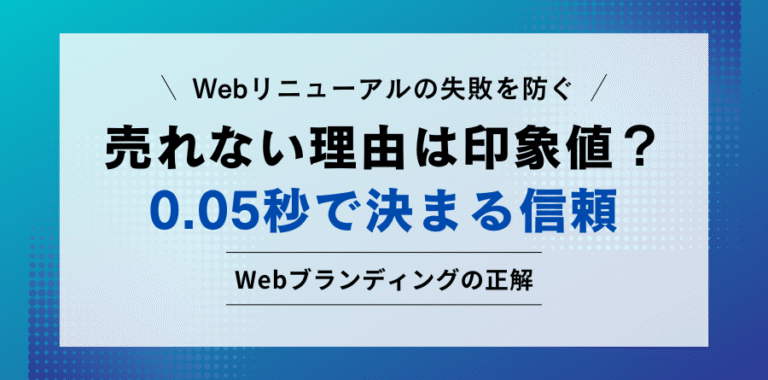
ブランディングの土台はWebにある|企業イメージを左右する“見えない印象設計”
企業のブランド価値は、今や広告やパンフレットだけでは決まりません。顧客が最初にその企業に触れる「Webサイト」こそが、最も影響力のあるブランド接点となっているか...
-

企業が「価格で選ばれる」から脱却するためのWeb戦略
「価格で比較されてしまい、競合に負ける…」「見積もりの話になると必ず値引き要求が来る…」 大阪のBtoB企業様からも、そんな切実なご相談をよくいただきます。 ...
-
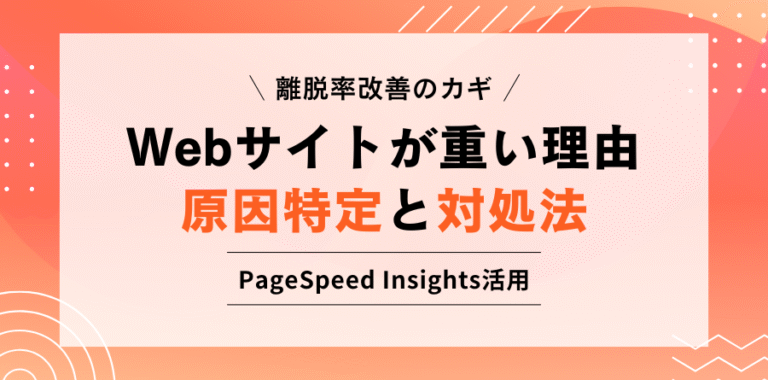
Webサイトが重い理由を解説!原因を知って対処する方法【表示速度改善】
普段Webサイトを利用していて「このサイト、表示されるのが遅いな(重いな)」と感じたことはありませんか? 知りたい情報があるのに画面がなかなか切り替わらないと...
